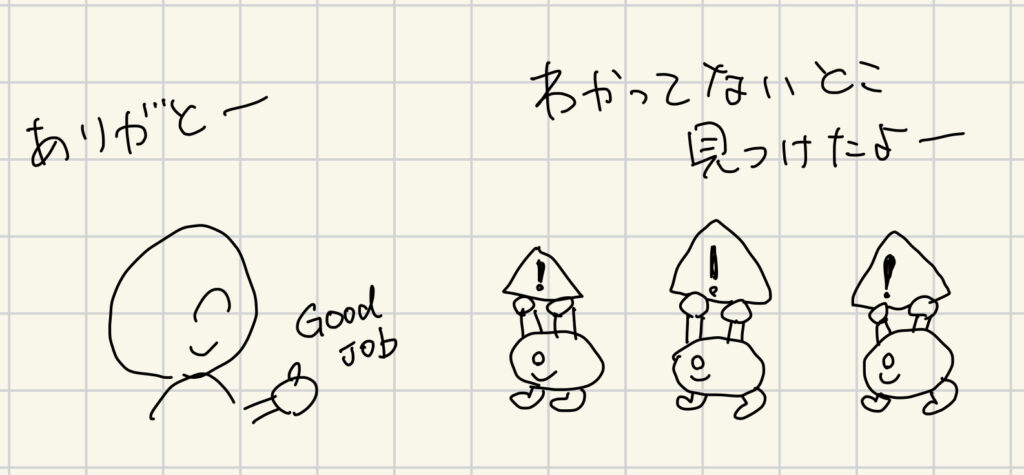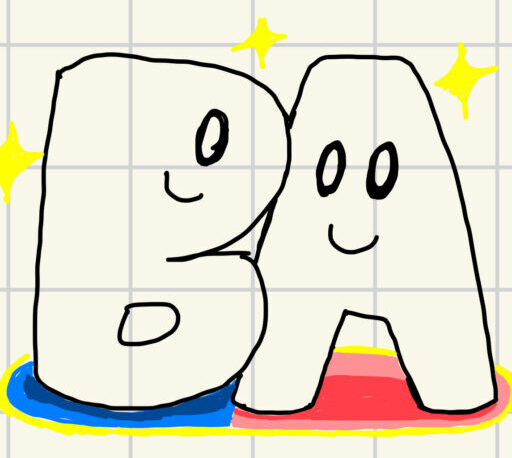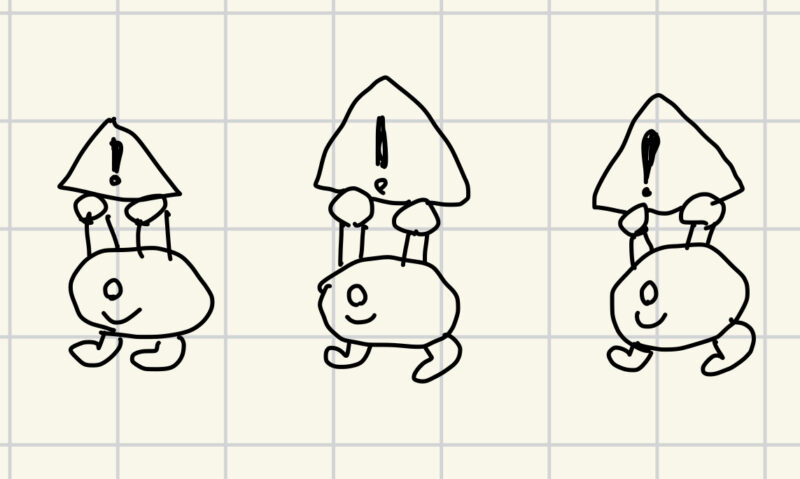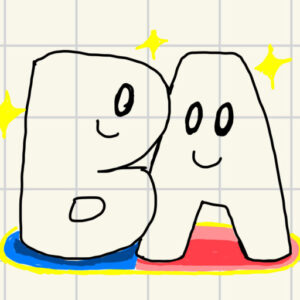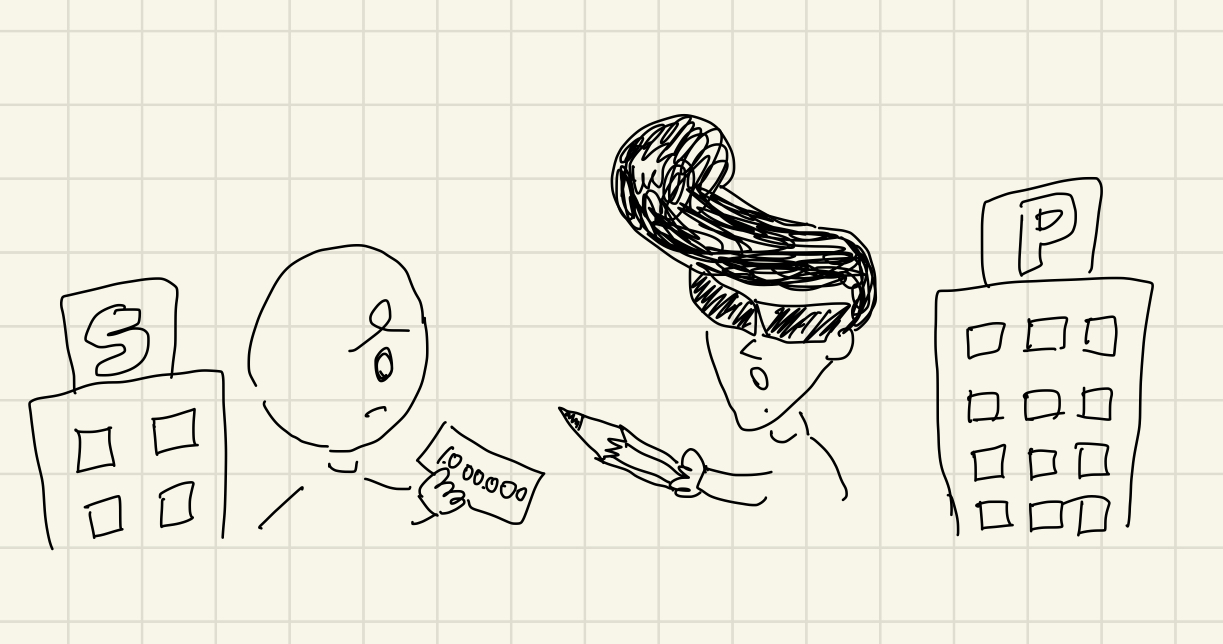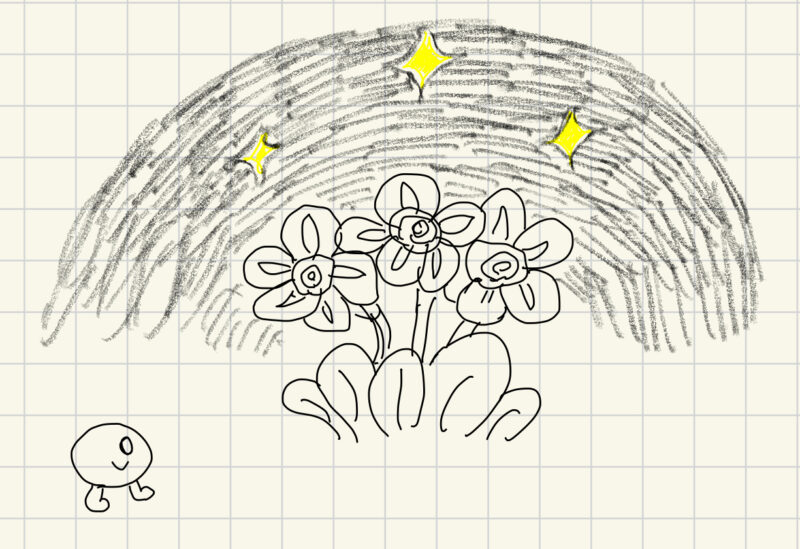簿記の勉強。皆さんどうやってやってますか?
小学校でも簿記の専門学校でも、まずは解けるようになることを目指して勉強していると思います。
今日はそんな「スクール勉強法」に対して、私が実践してる「BokiArt勉強法」を紹介したいと思います。
スクール勉強法
- 問題を解いてみる
- 採点をする
- 答え合わせをする
- 1に戻る
学校だと大体このような形で勉強していきますよね。
もちろんその前に座学がありますが、解いていく過程は上記のようなループだと思います。
このやり方、「1」で解けなかった問題、確かに「4」では解けると思います。
ただ、「4」で解けるのは、「3の答え合わせを覚えているから」です。
「理解したから解けた」わけではなく、解き方を覚えてるから「解けてしまっている」だけです。
何日かしてからもう一度同じ問題を解いてみると、丸っきり理解できていなかったことに気づくと思います。
以下の記事でも個人的な失敗談として記載しております。
Boki Art 勉強法
BokiArtでは以下の手順をお勧めします。
- 問題を解いてみる
- 採点をする
- 間違えた問題について「何が分かっていないか」をメモする
- 3のメモを見て不明点を調べる
- 1に戻る
スクール勉強法と比較すると「答え合わせ」をしていないのがわかります。
ここで、少し掘り下げて、問題を解く理由を考えてみましょう。
- テストは「ちゃんと分かっているかどうかチェックする為」に試験の人が作ったものです
- 問題を解くのは、テストの練習として「どこが分かってないかをチェックする為」のものです。
「答え合わせ」は、分かってなくても正解出来るので、目的の手段にはマッチしません。
せっかく間違えて、「分かってないところ」をあぶり出せたのなら、分かってないところを、そのままメモしましょう。
具体的には、解答用紙で「X」をつけたところに、質問を記載していきます。
例えば連結会計を勉強していた時の私のメモを見ると、以下のようなものがあります。
取得原価って個別と連結違う??
非支配株主持分って個別に載らない?
このような「質問メモ」を作ったら、次に「答え合わせ」はせずに、この「質問メモ」を見て不明点を調べていきます。
教科書の説明を改めて見てみる。WEBで調べてみる。Chat GPTやGeminiに聞いてみるのも有効です。
もちろん専門学校に行ってる人は先生にもう一度聞いてもいいです。
自分で、「質問メモ」について理解できて、自分なりに回答が出来たと思ったら、改めて問題を解いて見ましょう。
また間違えた場合は、まだ「質問メモ」に対して正しく理解ができないことになります。粘り強く調べていきましょう。
この勉強方法は、短期的には「答え合わせ」をするよりも時間がかかります。
しかし、「あ!この論点、ここと同じだ。でもここのポイントが違うみたいだな。こういう性質の差があるからか!」というように、いろんな仕訳や勘定科目の理解が深まります。
より本質的に理解ができるので、応用問題にも対応ができるようになってきます。
テストではもちろん正解することが大事ですが、その前の問題に間違えることはウエルカムです。
解き方を覚えて正解していく喜びももちろ大事ですが、「 」を見つける喜び、「 」を解消していく喜びも味わいながら勉強していきましょう!
このサイトの記事も、私の「質問メモ」から生まれたものばかりです。
皆さんも「Boki Art勉強法」是非試して見てください。